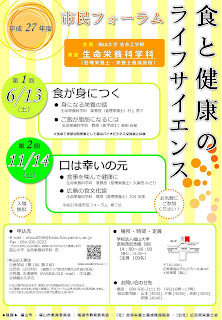遅くなりましたが、今回は4月に新しく国際経済学科に新しくメンバーとして加わった藤本浩由講師に自己紹介していただきます。
それでは藤本先生よろしくお願いします!
今年度から経済学部国際経済学科の講師に着任した藤本浩由と申します。マクロ経済学の講義を担当しています。
私の出身はここ、福山大学最寄り駅のある松永です。着任して2 か月近く、授業準備や日常業務に慣れるのにヘトヘトの毎日ですが、それでも超!地元の福山大学で教員として働ける幸せをかみしめています。大学教員としては新米ですが、早く馴染んで福山大学に貢献できるようにがんばります。
 |
| 研究室にて |
日本にいると当たり前のように手に入るものが、世界の多くの 国々では手に入らない。みなさんの大学生としての日々はまさにそういったものの一つです。ぜひ満喫していただきたいです。
ところで私が博論のトピックにアフリカの経済発展を選んだ背景 には、青年海外協力隊に参加し、ケニアという国の田舎の中学校で教員として働いた経験があります。大学時代は自分が海外に住むことになるなんてこれっぽっちも想像してなかったですが、卒業直前の思いつきレベルの勢いで参加してしまいました。案の定あまり貢献はできませんでしたが…大学を卒業して間もない、教員としての経験がほとんどない私の授業を、現地の子供たちが真剣に聞いてくれたことがすごくうれしかったことを、今でも鮮明に覚えています。
 |
| ケニアの中学校で生徒たちと |
ちな みに、好きなことは「貧乏旅行」、好きな本は「深夜特急」と「夏への扉」、好きな番組は「イッテQ」と「水曜どうでしょう」です。不愛想な疲れた顔をして歩いていますが、どうか気軽に声をかけてください!
学長から一言:国際経済学科ぴったりの、しかも地元出身の教員に来ていただきました。。。国際経済学科から、どんどん学生が海外に出ていくように、大学全体で支援していきますよ! 語学力より心意気です!!